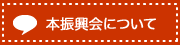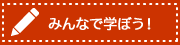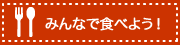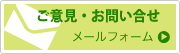HOME > みんなで学ぼう!> 野菜博物館(やさいはくぶつかん)> ながいもの部屋(へや)>ながいもが育つまで
ながいもが育つまで
4月
畑の準備
種いもをうえるまえに畑の準備をします。ながいもは、地中深く育っていきますので、根のとどく深さくらいまで、よく耕しておくことが大切です。浅く耕されていたり、石などがあると、地中に向かってのびようとするながいもの障害物になって、よい形に育たなくなってしまいます。トレンチャーという機械で、幅15センチメートル・深さ1メートルくらいに耕します。
種いもの準備
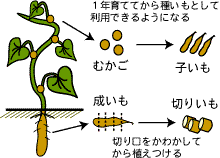 ながいもは花をつけますが、ほとんど(全くといっていいほど)種はできません。ですので、いもをつかって栽培します。種となる種いもは、地中にできる成いもを切って使う場合と、地上部の茎の部分にできる「むかご」を育てて種いもにする場合とがあります。
ながいもは花をつけますが、ほとんど(全くといっていいほど)種はできません。ですので、いもをつかって栽培します。種となる種いもは、地中にできる成いもを切って使う場合と、地上部の茎の部分にできる「むかご」を育てて種いもにする場合とがあります。
5月?6月
植えつけ
![]() 種いもを畑に植えつけます。かぶせる土は、あまり厚くしません。浅い方が、芽が出やすくなるからです。水はけをよくするために、畝を高くします。
種いもを畑に植えつけます。かぶせる土は、あまり厚くしません。浅い方が、芽が出やすくなるからです。水はけをよくするために、畝を高くします。
芽出し
![]() むかごや切りいもを用いた1年養成いもなどの種いもの場合、定芽をもっていますので、20日?30日ほどで芽がでてきます。切りいもをそのまま種いもとする場合は、芽が出るまで40日?50日ていど必要です。芽が出ると、茎のもとから根もでてきます。
むかごや切りいもを用いた1年養成いもなどの種いもの場合、定芽をもっていますので、20日?30日ほどで芽がでてきます。切りいもをそのまま種いもとする場合は、芽が出るまで40日?50日ていど必要です。芽が出ると、茎のもとから根もでてきます。
7月?9月
つる
 芽が出るとながいもの茎は、急速に生長します。茎はつるになっていて、右まきに、支柱またはネットにからまりながら、どんどんのびます。最初は、小さくまばらな葉も、つるがのびてゆくにしたがって、しだいに多くなってゆきます。
芽が出るとながいもの茎は、急速に生長します。茎はつるになっていて、右まきに、支柱またはネットにからまりながら、どんどんのびます。最初は、小さくまばらな葉も、つるがのびてゆくにしたがって、しだいに多くなってゆきます。
いもおよびむかごの形成
 つるがのび(2?3メートルまでのびます)、葉がおいしげるころになると、地中では、茎の根元にできた新しいいもが大きくなりはじめます。種いもは、消耗してなくなってしまいます。
つるがのび(2?3メートルまでのびます)、葉がおいしげるころになると、地中では、茎の根元にできた新しいいもが大きくなりはじめます。種いもは、消耗してなくなってしまいます。
このころ、「むかご」もできます。つるが下向きにたれさがった場合に、その葉と茎のあいだに、むかごが形成されます。このむかごは、地中のながいもと同じ性質をもっており、種いもにも食用にもなります。
10月?12月
収穫
 10月下旬ごろ葉や茎が黄色くなり、枯れてきたら、いよいよ収穫です。収穫は、11月?12月にかけて行われます。ながいもは、地中深くのびていますので、いもにそって深い穴をほり、ていねいに収穫します。掘取機での収穫の場合、支柱やネットを取りのぞいてから、作業を行います。
10月下旬ごろ葉や茎が黄色くなり、枯れてきたら、いよいよ収穫です。収穫は、11月?12月にかけて行われます。ながいもは、地中深くのびていますので、いもにそって深い穴をほり、ていねいに収穫します。掘取機での収穫の場合、支柱やネットを取りのぞいてから、作業を行います。
この時に収穫するのは、できたながいもの半分くらいです。あとの半分は、収穫せずに土の中で保存します。
貯蔵
 収穫したながいもは、土のついたまま冷蔵庫で保存し、順番に出して、洗って、選別し、段ボール箱につめて市場に出荷します。
収穫したながいもは、土のついたまま冷蔵庫で保存し、順番に出して、洗って、選別し、段ボール箱につめて市場に出荷します。
上十三広域農業振興会には、68,000コンテナ分のながいもが貯蔵できる低温貯蔵庫や、ながいも高速洗浄施設があります。
1月?3月
天然貯蔵
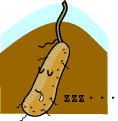 成熟したながいもは、休眠に入ります。休眠に入ると土の中で貯蔵することが可能です。土の中に植えたままだと、いもからまた新しい芽が出てきてしまいそうですが、ながいもは一定期間休眠した後でないと発芽しません。この性質を利用して、春まで、土の中で休眠状態のまま保存します。
成熟したながいもは、休眠に入ります。休眠に入ると土の中で貯蔵することが可能です。土の中に植えたままだと、いもからまた新しい芽が出てきてしまいそうですが、ながいもは一定期間休眠した後でないと発芽しません。この性質を利用して、春まで、土の中で休眠状態のまま保存します。
こうして、土の中で保存することにより、貯蔵するための場所や冷蔵保存するための電気代を節約することができます。貯蔵の手間がかからないだけではなく、2回に分けて収穫するので作業の労力も分配されます。
冬を土の中でこしたながいもは、休眠からさめて芽が出るまえの、4月下旬までに収穫されます。この時期は、新しいながいもの栽培準備の行われるころでもあります。
Copyright © 一般社団法人 上十三広域農業振興会 All Rights Reserved.